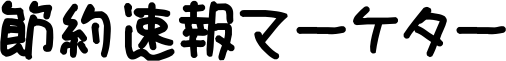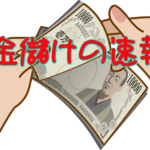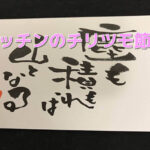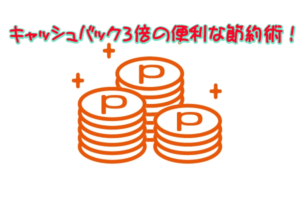おばあちゃんの知恵袋は○○○いらずでお掃除ができる
床用洗剤いらず! 玄関の三和土は濡らした新聞紙で
玄関の三和土(たたき)に濡らした新聞紙をちぎってまいて、ほうきで集めながら掃くと、ほこりを立てずにお掃除できます。こびりついた泥汚れも、濡らした新聞紙でふけば洗剤なしでキレイに!

漂白剤いらず! 茶渋は塩で取る
湯のみやカップの気になる茶渋は、指に塩をつけて、または軽く濡らしたスポンジに塩をひとつまみふってこすり落としましょう。塩が研磨剤の役目になります。

フローリングワイパーシートいらず! 着古した服で床掃除
ワイパーで床をふくなら、使い捨てシートのかわりに着古した服を切って使って節約を。ゴミを吸着しやすい化学繊維がベターです。

クレンザーいらず! 鍋の黒ずみは歯磨き粉で
洗剤だけでは落とし切れない鍋の黒ずみには、歯磨き粉がオススメです。
使い古しの歯ブラシにつけてこすってみてください。

ワックスいらず! 床磨きは米のとぎ汁で
米のとぎ汁には汚れ落としとワックスの効果があるので、床磨きに活用できます。とぎ汁にぞうきんを浸して固くしぼって木目に沿ってふいたら、床がピカピカに!

除草剤いらず! ゆで汁を雑草に
ガーデニングや家庭菜園でやっかいな雑草対策は、ゆで汁や熱湯をかけるといいです。
野菜のゆで汁を2度使いしましょう。
ただし、大切な花や作物にかからないように注意してください。

専用クリーナーいらず! 家具は大根おろしで磨く
木製家具の手あかの黒ずみは、大根おろしで落とせます。
それは、大根に脱色効果のある酵素が含まれているからです。
布につけてこするように磨くと取れるます。

ボトル用スポンジいらず! 卵のカラで水筒洗い
細長い水筒は底のほうを洗うのが大変です。
そこで、粗めにくだいた卵のカラと少量の水を入れてフタを閉めて、上下によくふります。
カシャカシャとカラが当たって汚れを落としてくれます。

買い替えいらず! シャワーヘッドはお酢で目詰まり解消
シャワーヘッドの目詰まりは、水道水のミネラル分が原因です。
水の出が悪くなったら、洗面器に熱めの湯と酢2分の1カップを注ぎ、取りはずしたシャワーヘッドをひと晩浸します。

専用ブラシいらず! 古靴下でブラインドふき
古い靴下はブラインドのふき掃除にとても便利です。
靴下を水で湿らせて手にはめて、ブラインドの羽根を1枚ずつはさんでふいていけば、ぞうきんを使うよりずっと手軽ですよ。

おばあちゃんの知恵袋で洗剤がわりになる節約素材
重曹
エコ掃除に欠かせない重曹は弱アルカリ性です。
酸性の油汚れを中和して落とし、お湯や酢と混ぜると発泡して汚れを浮かせます。
また粒子が細かいので研磨剤になり、ニオイや湿気を吸着します。


・重曹ペーストで:重曹と水を3対1の割合で混ぜ、ペースト状に練って密閉容器に保存。ガス台の油汚れや洗面台の蛇口のくもりを落とす。
・重曹水で:重曹大さじ2を水500ccに溶かしてスプレーボトルに。冷蔵庫のふき掃除などに。
米のとぎ汁
米のとぎ汁には脂質、でんぷん質、タンパク質など成分が豊富に含まれ、汚れを落とす働きがあるので食器のつけ置きに最適です。
保湿効果もあるため洗髪や洗顔にも使えます。
1回目のとぎ汁は汚れが含まれるので、2回目が成分も濃くオススメてす。

茶がら
緑茶に含まれるタンニンは殺菌や消臭作用をもち、軽い油汚れも落とします。
お茶パックに入れてスポンジのように食器を洗ったり、キッチンのシンク磨きにピッタリです。
また、畳、フローリング、玄関の三和土に湿った茶がらをまいてほうきで掃くと、うまくほこりが取れます。

酢・レモン
弱酸性の酢やレモンは、水あかや石けんカスなどアルカリ性の汚れを落とすのが得意。洗面室や浴室の掃除にオススメです。
さらに殺菌・漂白・消臭作用もあります。

みかんの皮
みかんの皮に含まれている精油成分には、油汚れを落とす強力なパワーあります。
食器のギトギト油に、油性マジックやクレヨンの落書きも、みかんの皮でこすれば落ちるはずです。

塩
塩には汚れを落ちやすくする性質と除菌効果があり、おまけに塩粒による研磨作用もあるので、いわば天然のクレンザーです。
まな板の洗浄やシンク磨きに向いています。

卵のカラ
卵のカラは捨てず、麺棒でくだいてクレンザーがわりにしましょう。
こびりついた汚れより固く、金属やガラスよりやわらかいので、傷をつけずに汚れを落とせるスグレモノです。

おばあちゃんの知恵袋で脱臭剤いらず!
台所にはコーヒーかす、アルミホイル、角砂糖、みかんの皮
生ゴミには完全に乾燥させたコーヒーかすをかけ、排水口のカゴには小さく丸めたアルミホイルか十円玉を入れておきます。
水筒には角砂糖1個を入れておきます。

靴には十円玉、新聞紙、乾燥剤
靴の不快なニオイは、汗で湿気がこもって雑菌が繁殖するからです。
対策は、脱いだあとには菌の繁殖を抑える銅製(含有95%)の十円玉を片足に5枚ほど入れるか、丸めた新聞紙か食品についていた乾燥剤を入れて除湿を。

室内には茶がら、酢、濡れタオル
乾燥させた茶がらを煎ると、嫌なニオイにかわってお茶の香りが広がります。
古い茶葉でもOK。日常の生活臭はコップに酢を入れ、空気が通るところに置きます。

根のついた野菜は再生栽培!
豆苗のように、野菜の中には切れ端を使って家で再生栽培できるものも多いすね。
ねぎは根元を3~4cm残して使い、残した部分を土に植えて育てて食べられます。
コマツナの根も同様で、にんじんはヘタを水に浸すと葉っぱが伸びて収穫できます。

かた〜いお肉は炭酸飲料でやわらかく
安いお肉は、かたいから煮るのに時間がかかって光熱費がアップします。
ビールやコーラなどの炭酸飲料に10分ほど漬けるとやわらかくなります。
炭酸は抜けていても大丈夫です。

古米はサラダ油で新米っぽく♪
風味が落ちた古米は、水が透明になるまでしっかりとぐ。水を入れるときに米2合に対して小さじ1/2杯のサラダ油を加えて3時間つけて炊きます。

新じゃがはスプーンで皮をむいてムダなく!
春に出る新じゃがは皮が薄く皮ごとや皮を薄くむいて調理するのがいちばん効率よく栄養をとれます。
じゃがいもにスプーンのふちを当ててこすると皮がスルリとむけます。

お餅はからしと保存が長持ちのヒケツ
あまり日持ちしないお餅は、余ったら密封できる容器に粉からしを水で溶いたものと一緒に保存します。
辛み成分が菌を抑えて長くもちます。
市販のチューブ入りのからし、またはわさびでもOK。

広告アコーディオンでキッチンペーパーを節約
揚げ物の油切りには折り込みチラシを利用します。
チラシを何枚か重ね、約2cmのじゃばら折りにしてから、少し広げて揚げ物をのせます。

タオル保温でガス代節約
煮物は煮汁が沸騰したら、5~10分弱火で煮て火を止めます。
鍋ごと新聞紙、タオルの順で包んで約20分。
塩分や糖分、うまみなどは冷めるときに浸透します。

固まった砂糖は水をかければ大丈夫
砂糖は水分が抜けるとカチコチに固まって、とても不便ですよね!
それなら霧吹きで軽く水をかけてスプーンで崩します。
かけすぎると溶けるので加減してくださいね。

しょうがは水入りの容器で長~く保存OK
しょうがは容器に入れた水に浸して冷蔵庫で保存して3日に1度、水の入れ替えをします。
薬味で使わないなら乾燥しょうがで保存するのもオススメです。
薄切りにして並べて、天日干しは2日、室内なら1週間で完成します。

かまぼこ板はちょい切りまな板にリサイクル!
かまぼこ板は、小さいけれど分厚くて丈夫です。
捨てずにミニまな板として再利用できます。

ペットボトルのキャップで軽量スプーンいらず!
初めて作る料理はレシピどおりに調味料を入れたいけれど、軽量スプーンがないなんて時ありますよね!
そんなときの代用品は約7.5ccに規格が統一されているペットボトルのキャップを利用します。

おばあちゃんの知恵袋で余った○○○はこう使う!

大根のおろし汁はニキビ予防に
大根は酵素のリパーゼがニキビの脂肪を分解して、殺菌効果もあります。

緑茶のティーバッグを化粧水に
殺菌作用のある緑茶はティーバッグで飲みましょう。
使い終わった出がらしのティーバッグでそのままお肌をパッティングします。

大根の葉は干して入浴剤に
大根1株分の葉をざく切りして、ざるに広げて陰干しをします。
カラカラに乾いたら木綿の布に包んで湯船に入れて水から沸かします。

古いあずきはカイロに
綿タオル(16×10cm)を半分に折って両脇2辺を縫い、裏返してあずき約50gを入れてあき口を縫って完成します。

麺のゆで汁はヘアパックに
うどん、そば、ラーメンなどのゆで汁で髪をパックして、しばらく置いて洗い流します。

キャベツの外葉は熱冷ましに
解熱作用があるといわれるキャベツ。
発熱したら、ふだん捨ててしまう外側の大きな葉をしっかり洗って水けをきって、かぶるように頭を包みます。

まとめ
結構、「なるほど」と感じた内容もあったのではないでしょう?
あなたが、関心のあったものだけでも試してみてはいぎでしょうか。