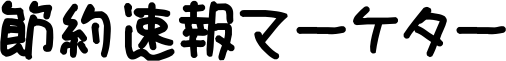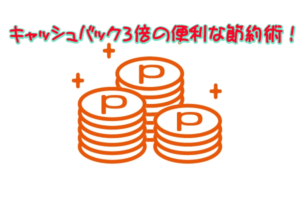「もう量はさほど食べないから、少量でもおいしいもの食べたい」「健康が何より大事だから、多少高くても体にいいものが食べたい」といった理由の人もいることでしょう。
しかし実は、「節約したいお金」でも、食費は毎回、上位に入ります。
「世帯の人数が減ったのだから食費も減らしたいが、意外と減らない」「年金生活で貯金を減らさないために、身近なところから節約したい」などの声が多いわけです。
スポンサーリンク冷蔵庫の使い方で食品をダメにしない
食べるものはケチりたくない。
でも食費は減らしたい。
ある意味、矛盾している要求をどう満たせばいいのでしょう。
そこで目を付けたのが、冷蔵庫の使い方です。
「冷蔵庫の奥で青菜がしなびている」「あれ? 使いかけのからしのチューブが2本もある」。
実はこうした積み重ねが食費のムダを生みます。
横浜市の調査によると、買ったのに使いきれずに捨てた食材や食べ残しなどを合わせると、年間で一人当たり2万2000円分に及ぶそうです。
ということは、食品そのものはケチらずとも、食べきれずに捨てたり、忘れていて腐らせたりというムダを出さないように心がければ、年間数万円もの食費を節約できることになります。
そんな、ムダをなくすための冷蔵庫の条件として「見やすい」「まとまっている」「取り出しやすい」の3つです。
まず見やすさについては、今ある食材を把握しやすければ、気づかない間に野菜が傷んだり、食べ忘れたりするのを防げます。


また、冷蔵庫内で散らばりやすい調味料や使いかけの野菜などはまとめておくことです。
見落として同じものを買うのを予防し、使いかけの食材を優先的に使おうという意識も生まれます。
最後に取り出しやすさも重要です。重い容器同士を重ねたり、冷蔵庫の奥に食材をしまい込む、それだけで手が遠のき、余らせがちになります。
そもそも、冷蔵庫の扉を20秒開けていると庫内の温度が10度ほど上がってしまいます。
見つけやすく取り出しやすいことは、冷蔵庫の開閉時間の短縮になり、電気代の節約にもつながります。
詰め込まない冷蔵庫の使い方
では具体的にどうすればよいのでしょう?
まず冷蔵室の場合。スペースが広い分、見落としが発生しがちになります。

見落としを防ぐためには、
1. パンパンに詰め込まず、収納量自体を7割くらいにして見やすくすることです。
2. 可能なら棚板の奥行きを半分にして死角を減らしましょう。早く食べたほうがいい作り置きおかずは、中身が見える透明な容器に入れることです。
3.一緒に使うもの、例えば朝食のバター、ジャム、ヨーグルトなどは1つのトレイにまとめておくことで取り出しやすく、残量が把握しやすくなるので、無駄を防げます。

次にドアポケットですが、ここは開閉による温度変化が激しいため、生鮮食品の保存には不向きです。
調味料や飲み物を入れて、使い忘れや余分買いを防ぐ工夫をしましょう。
ポイントは、
1. 使用頻度が低いものには、開封日を書いたシールなどを貼っておくことで、ものによるが、2〜3カ月以内に使い切るよう意識しましょう。
2. 行方不明になりやすいチューブ調味料などは1カ所にまとめましょう。
在庫を把握して、余分に買ってしまうのを防ぎましょう。