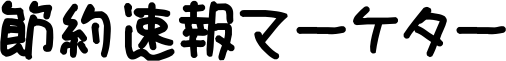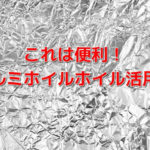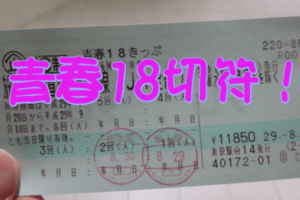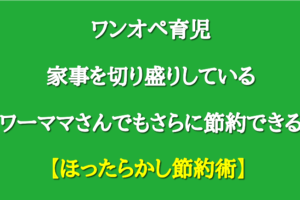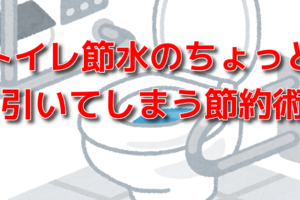というわけで、この章ではコロナで使えなく食費の節約について考えてみましょう。
スポンサーリンクスーパー特売セールの食費の節約術
スーパーの特売セールをチラシでチェックしたり、値引きシール品を狙って閉店間際に出かけたり、
「5%引きデー」にまとめ買いするというのが食費節約の定番ですよね。
また、スーパーごとに異なる特売日をはしごするなど、複数の店を回っている人もいるでしょう。
しかし、コロナ下ではどうか。
買い物に関する意識調査によると、毎日スーパーに行っていた人の割合は、コロナ前の21.7%から現在では12.3%とほぼ半減しました。
一方、 「週に1回程度」は24.5%から33.9%と9.4ポイント増、「月に2回程度」は1.3ポイント増、「月に1回程度」は0.3ポイント増と、全体的に来店頻度が低くなっています。
さらに、店でに滞在する時間も短くなりました。
「20分未満」が31.9%から45.7%と約1.5倍になったのに対し、「30分以上」(「30分~1時間未満」「1~2時間未満」「2時間以上」を合算)は31.8%から20.6%とダウン。
そのため、買い物の仕方も「予定していたものだけを購入」が16.1%から30.4%と約2倍に急増し、「8割は予定せず、店頭で判断したものを購入」が20.3%から9.2%と半減しました。

特売品での食費の節約術は絶滅か

こまめに店頭に行ってその日の特売品を買って、そこからメニューをひねり出すパターンと、先に1週間分のメニューを決めて買いものするパターンです。

先の調査によると、買い物にいく店を選ぶ理由は 「お店が近い」が67.7%となり、商品が安いからという理由を上回っています。
移動時間を短くしたい心理があるわけで、複数の店舗をはしごすることも減っているでしょう。
巣ごもり生活で購入量が増えているだけでなく、こうした買い物行動の変化も食費を押し上げていると思わます。
では、今後の食費節約はどうあるべきか。
まずは、「まとめ買いをベースにした予算立て」をしっかり行うことです。
月の食費予算から米など大物の分を除き、残りを日割りで計算します。
買い物に行く頻度に合わせて、何日分を買うのかを掛け算する。
日用品を同じ店で買うことが多いなら、その予算を合計してもいいでしょう。
現金派は、とにかくその金額しか財布に入れないで出かけることですね。
キャッシュレス派は「あといくら、使えるお金が残っているか」を管理するのがポイントです。
それには、プリペイド式電子マネーを食費専用にするのが手っ取り早いですね。
1週間分の予算額をチャージしておくのが管理がしやすいです。
[/box]次に予算内に収めるための買い方だが、売り場の配置に任せず、「買い物は肉・魚売り場から」がいいです。
特売品や単価の安いものからあれこれ買っていると、気づくと予算オーバーになっていることがあるのです。
まず価格が高いメインの肉や魚を確保して、残金の範囲でほかの食材や特売品を買うほうがいいでしょう。
なお、“3品まとめ買いで割引に”というセット商法は、平時なら余計な買いものが増える元なのでお勧めしないが、コロナ下のまとめ買い用と考えれば悪くはないです。


豚肉とひき肉と切り身魚をバラバラ選んで買うのではなく、豚肉×3、ひき肉×2+切り身魚×1というように。
異なる3品を中途半端な量で買うよりも、単品の分量を2~3倍にしたほうが料理には使いやすいでしょう。
買い物するにも不自由になったとはいえ、悪いことばかりではありません。
買い物回数が減ることで、「買わなくてよかったもの」も減る作用があります。
金額を計算し、適正な予算内で適量を買う。
シンプルですが、食費節約はそれに尽きますね。
コロナでも関係ない我が家の食費の節約術

1. 冷蔵庫などに余っている食材を確認する
2. 余っている食材が使えるようなメニューを1週間分決める
3. 近くのスーパーで食材を買う(車で3分)
4. 野菜や果物はスーパー近くにある直売所で買う(直売所は安い)
5. 支払いは必ずキャッシュレス決済する(ポイント2重取り)
6. 食材以外の日用品はあらかじめネットで約1年分を安く購入しておくため、リアル店舗では買わない
7. 肉や魚はアルミホイルで包み冷凍しておく
まとめ
ぶっちゃけ、1円や10円単位の節約はあまり意味がないというか、効果がうすいですしね。
どうせ、するなら効率的な節約をするべきですし、労力も減ります。